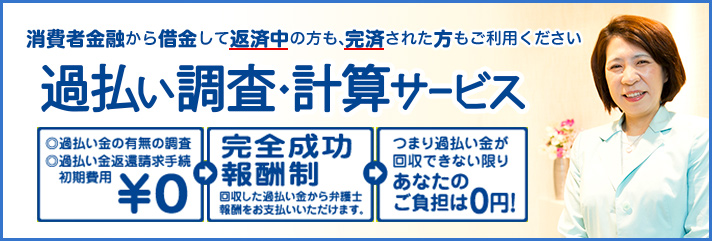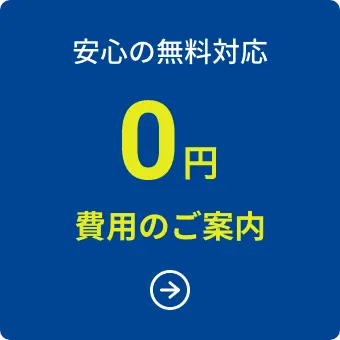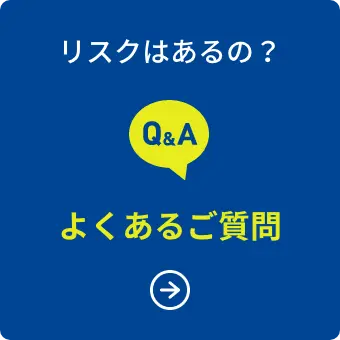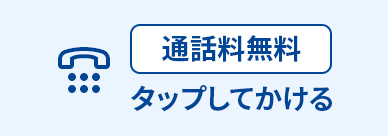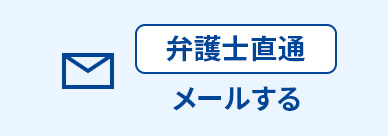過払金に関わる利息制限法と出資法の関係
はじめに
過払金は、金銭消費貸借契約において、利息制限法所定の制限利率を超える利率が設定されていた場合に発生します。具体的には、元本が10万円未満であれば年利20%を超える場合に、元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%を超える場合に、元本が100万円以上であれば年利15%を超える場合に過払金が発生します(利息制限法1条)。
このように、利息制限法は金銭消費貸借契約における上限利率を定めていますが、上限利率を定める法律には出資法もあります。ここでは、上限利率に関わる利息制限法と出資法の関係についてみていきます。
利息制限法と出資法の関係
利息制限法と出資法は、金銭消費貸借契約における利率について、それぞれ以下のように定めています。
利息制限法1条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
| 一 | 元本の額が10万円未満の場合 年2割 |
|---|---|
| 二 | 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 |
| 三 | 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分 |
出資法5条2項
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
出資法5条3項
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
利息制限法は、上限利率を超える部分を無効と規定していますが、刑事罰については定めていません。そのため、利息制限法は民事上の上限利率を定めるものと言えます。
これに対し、出資法は、上限利率を超える場合には刑事罰を科すと定めています。そのため、出資法は、民事上無効になるだけでなく、刑事罰が科される利率を定めるものと言えます。
出資法の上限利率の推移
利息制限法と出資法の関係は以上の通りですが、出資法の上限利率は下記のように徐々に引き下げられてきました。
| 昭和58年10月31日まで | 年109.5% |
|---|---|
| 昭和58年11月1日~昭和61年10月31日まで | 年73% |
| 昭和61年11月1日~平成3年10月31日まで | 年54.75% |
| 平成3年11月1日~平成12年5月31日まで | 年40.004% |
| 平成12年6月1日~平成22年6月17日まで | 年29.2% |
| 平成22年6月18日~ | 年20% |
現在の年20%の利率でも相当大きな利息ですが、昭和58年10月31日までの年109.5%となると、1年借りると2倍以上の金額を返さないといけないことになりますので、途方もない金額と言えます。あまりに高利であるために、サラ金問題・商工ローン問題が発生し、それに対応するために徐々に引き下げられてきたものと言えます。
出資法の上限利率以下ではあるものの、利息制限法の上限利率を超える利率(グレーゾーン金利)について
上記の通り、利息制限法は民事上の上限利率を定めるもので、上限利率を超える部分は民事上無効です。ただ、利息制限法の上限利率を超えても、出資法の上限利率を超えなければ刑事罰は課されません。また、利息制限法の上限利率を超える部分は民事上無効と記載しましたが、平成22年6月17日までは、一定の要件のもと利息制限法の上限利率を超える部分を民事上有効とする貸金業法のみなし弁済規定がありました。さらに、以下の最高裁判決により実質的に無効化されたとされるものの、平成22年6月17日までは、利息制限法自体に、法定利率を超える制限利息を「任意に支払ったときは‥その返還を請求することができない」との規定がありました。
・ 最高裁判所昭和44年11月25日第三小法廷判決 民集第23巻11号2137頁
そのため、消費者金融とクレジットカード会社は、出資法の上限利率以下ではあるものの、利息制限法の上限利率を超える利率(グレーゾーン金利)で貸付をしてきました。ただ、グレーゾーン金利は、以下の最高裁判決等によりほとんどのケースで民事上無効になるものと判断されました。
・ 最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決 民集第60巻1号1頁
そのため、平成18年頃以降は、貸金業者に対する過払金返還請求が急増することになりました。一方で、グレーゾーン金利が無効と判断されたことに伴い、多くの貸金業者は平成19年頃から契約利率について利息制限法の上限利率以下に引き下げを行いました。
弁護士によるまとめ
以上、過払金に関わる利息制限法・出資法の関係について見てきました。細かく見ていくと複雑な話になりますが、貸金業者は、出資法の上限利率以下ではあるものの利息制限法の上限利率を超える利率(グレーゾーン金利)を設定していたものの、グレーゾーン金利が無効と判断されたため、過払金請求が可能になったと言えます。このようなことは過払金を請求する際にあまり意識することはないかもしれませんが、過払金が発生することになった理由は以上の通りですので、過払金請求をする際には知っておいてもいいかもしれません。