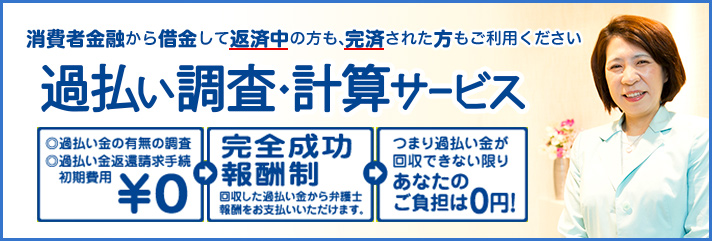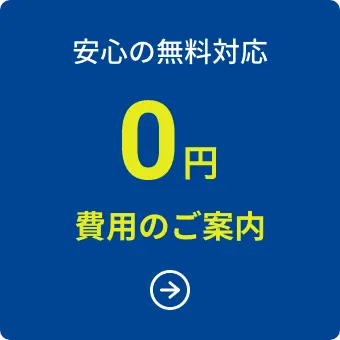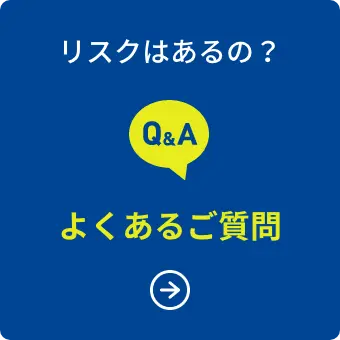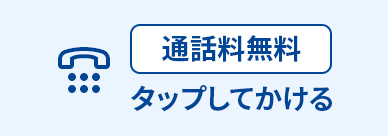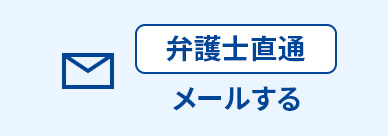過払金回収の際の不動産担保ローンの問題点
はじめに
消費者金融(アコム・プロミス・アイフル・レイク等)から借入は、無担保であることが多いですが、所有している不動産を担保に入れた上での借入ということもあります。不動産を担保に入れた上での借入は、不動産担保ローンということがあります。このページでは、過払金回収の際に問題になることがある不動産担保ローンについて見ていきます。
不動産担保ローンの特徴
不動産担保ローンは、借入をする人が所有している自宅などの不動産を担保に入れて、消費者金融等から借入をするものです。無担保での借入と比較すると以下のような特徴があります。
無担保での借入と比較した場合の不動産担保ローンの特徴
①自宅などの不動産に抵当権が設定される
②返済が滞ると抵当権を実行され、不動産を失う可能性がある
③借入枠が数百万円程度と大きいことが多い
④借入利率は低いことが多く、平成20年頃より前でも利息制限法内の利率になっていることがある
⑤借入と返済が繰り返されるリボ取引ではなく、一度借入をしたら返済のみになる取引がよくある
⑥利息制限法内の取引になっていることがあるため、無担保ローンと比較して過払金が発生している確率が低い
⑦一方で、借入枠が大きいため、過払金が発生しているとなると、数百万円~1000万円超と多額のケースがある
⑧自宅が抵当に入っているため、約定債務を完済しないと過払金を請求しづらいケースが多い
⑨借入当初から不動産担保ローンということもあるものの、不動産担保ローンの前に無担保ローンでの取引が先行していることがよくある
以上の不動産担保ローンの特徴のうち、⑨の点について、先行する無担保ローンと後続の不動産担保ローンを一連の取引として過払金の算定ができるかが問題になることがあります。
無担保ローンと不動産担保ローンの一連計算について
無担保ローンの取引に引き続き、不動産担保ローンの取引が行われる場合、無担保ローンの取引は完済・解約、新たに不動産担保ローンの契約をして取引が行われるというのが一般的です。ここで取引が分断しているとなると、発生している過払金が小さくなりますし、無担保ローンの完済・解約が10年以上前で、不動産担保ローンの契約利率が利息制限法内であれば、過払金は回収できなくなります。そのため、無担保ローンと不動産担保ローンの一連計算ができるかが大きな問題となります。
争点についての最高裁判所の判例
無担保ローンと不動産担保ローンの一連計算が可能かどうかについては、以下の最高裁判所の判例があります(読みやすくするために、最高裁判所の原文に一部改変を加えています)。
最高裁判所平成24年9月11日判決
「被上告人(借主)とA(消費者金融会社)との間では本件第1契約が締結され、これに基づく取引が続けられた後、改めて本件第2契約が締結されたところ、本件第1契約は無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約であるのに対し、本件第2契約は不動産に根抵当権を設定した上で1回に確定金額を貸し付け毎月元利金の均等額を分割弁済するという約定の金銭消費貸借契約であるから、両契約は契約形態や契約条件において大きく異なり、本件第2契約の締結時後は、本件第2契約に基づく借入金債務の弁済のみが続けられている。そうすると、本件第2契約がAの担当者に勧められて締結されたものであり、これに基づく借入金の一部が本件第1契約に基づく約定残債務の弁済に充てられ、被上告人にはその残額のみが現実に交付されたこと、本件第1契約に基づく取引は長期にわたって継続しており、本件第2契約が締結された時点では当事者間に他に債務を生じさせる契約がなかったことなどという程度の事情しか認められず、それ以上に当事者が本件第1契約及び本件第2契約に基づく各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしているとみるべき事情のうかがわれない本件においては、本件第1契約に基づく取引と本件第2契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することは困難である。」
この判決では、リボルビング方式の無担保ローン取引と、一度借り入れた後返済のみを行う不動産担保ローン取引の一連計算はできないと判断されています。ただし、無担保ローンと不動産担保ローンについて、全ての場合について一連計算ができないと判断したわけではない点に注意が必要です。この点は、上記判決における田原睦夫裁判官の補足意見に記載されています。
田原睦夫裁判官の補足意見
「当初のリボ契約の後に締結された担保権付契約が、同様にリボ契約である場合には、両契約間の基本的な相違は、担保権設定の有無の点だけであるから、両契約に基づく各取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるか否かは、法廷意見の引用する当審の判例に従って判断することに何ら問題はない。」
この補足意見では、無担保ローンと不動産担保ローンがいずれもリボ契約である場合は、取引の一連性について判断した最高裁判所の内容にしたがって、一連取引と判断できる可能性があることが示されています。最高裁判所の判決によると、第1の基本契約と第2の基本契約を一連計算できるかは、①第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ、②これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、③第1の基本契約についての契約書の返還の有無、④借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯、⑦第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、判断するものとされています(最高裁判所平成20年1月18日判決)。
無担保ローンと不動産担保ローンの場合、②の中断期間は0日ですので、この点は、借主に有利な要素になります。一方、⑦について、利率・遅延損害金利率・借入枠が異なるケースであれば、借主に不利な要素になります。無担保ローンと不動産担保ローンがいずれもリボ契約である場合は、以上の点等を考慮して取引の一連性や和解の金額を検討する必要があります。
弁護士によるまとめ
以上、不動産担保ローンの特徴や無担保ローンと一連計算等について記載しました。不動産担保ローンは利率が低く、過払金が出ないケースもありますが、借入枠が大きいため、過払金が出るとなると数百万円~1000万円超と大きなものになるケースがあります。消費者金融の不動産担保ローンを完済して、過払金があるか調べたいという方は、みお綜合法律事務所の無料過払金調査をご利用ください。