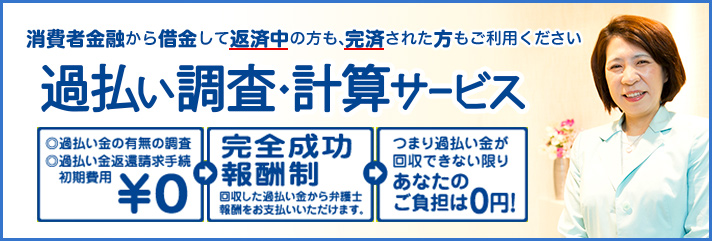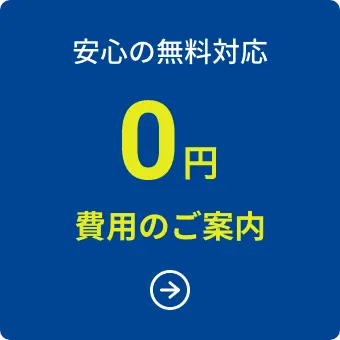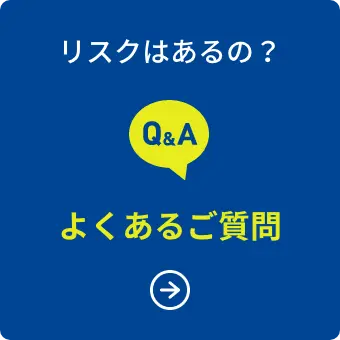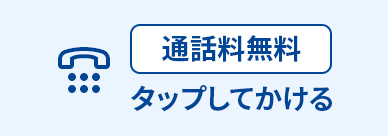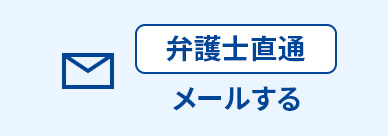過払金裁判の管轄(過払金の裁判はどこの裁判所で行うか)
はじめに
過払金の手続きを弁護士に依頼して、消費者金融やクレジットカード会社に過払金を請求する場合、交渉で回収するケースと、裁判で回収するケースがあります。交渉と裁判の違いは、下記のページで解説しました。
過払金請求における交渉と裁判の違い
交渉は弁護士と対象となる業者との交渉ですので、どこの裁判所で手続きをするかは考える必要がありません。一方、交渉では解決せず、訴訟する場合は、どこの裁判所で手続きをするかを考える必要があります。依頼をした弁護士事務所から近い裁判所で裁判ができた方が、弁護士費用負担が軽くなることがあるため、過払金請求を弁護士に依頼した方にも利害関係がある問題になります。
この点、どこの裁判所で手続きをする必要があるかは、裁判管轄の問題であり、民事訴訟法や裁判所法に規定があります。以下では、法律の規定に基づき、過払金の訴訟をどの裁判所に起こすことになるかを見ていきます。
過払金訴訟の管轄
(1)管轄の種類
過払金に関する裁判の管轄には、以下の二つがあります。
| ア | 請求する金額によって地方裁判所で手続きをするか、簡易裁判所で手続きをするかという事物管轄 |
|---|---|
| イ | 所在地を異にする同種の裁判所(地方裁判所または簡易裁判所)の中で、どこの裁判所で手続きをするかという土地管轄 |
(2)事物管轄
ア 基本的な考え方
地方裁判所で手続きをするか、簡易裁判所で手続きをするかの点ですが、過払金の額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所になります。根拠規定は以下の条文です。
裁判所法24条
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟
(以下省略)
裁判所法33条
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求
(以下省略)
簡易裁判所は140万円を超えない請求について管轄があり、それ以外の140万円を超える請求は地方裁判所に管轄があることになります。
イ 過払金に対する利息の取扱い
過払金の額が140万円を超えるかどうかは、過払金元本で判断され、過払金に対する利息は含みません。この点の根拠規定は以下の条文です。
民事訴訟法9条2項
果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
この条文の中に「果実」という文言があり、一般的な用語とは異なるかもしれませんが、過払金利息は「果実」に含まれると考えられています。そのため、地方裁判所で手続きをするか、簡易裁判所で手続きをするかを考える際には、過払金利息は考慮しません。例えば、過払金元金が139万円、過払金利息が65万円の合計204万円の場合は、簡易裁判所での手続きになる一方、過払金元金が141万円、過払金利息が1万円の合計142万円の場合は、地方裁判所での手続きになります。
ウ 複数の消費者金融・クレジットカード会社に対する過払金請求をまとめて裁判する場合
例えば、3社に対して過払金があり、A社に対する過払金元金は50万円、B社に対する過払金元金は60万円、C社に対する過払金元金は70万円という場合、3社別々に簡易裁判所で手続きをする必要があるか、3社まとめて地方裁判所で手続きができるかという問題があります。
この問題については、最高裁判所平成23年5月18日第二小法廷決定があり、3社に対する過払金元金を合計した180万円を前提に、地方裁判所で手続きすることができると判断されています。
複数社に対する過払金の元金の合計が140万円を超える場合に地方裁判所でまとめて手続きできれば、過払金を請求する側の手続き負担が少なくなりますので、請求する側に有利な判断をした裁判例といえます。
(3)土地管轄
過払金請求に関連する土地管轄の規定には、以下のものがあります。どの場所の裁判所に裁判を起こせるかの問題ですので、事物管轄より請求する側にとって利害関係が大きい問題と言えます。
民事訴訟法4条1項
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法4条4項
法人‥の普通裁判籍は、その主たる事務所‥により‥定まる。
民事訴訟法5条
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え 義務履行地
(以下省略)
民法484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
民事訴訟法4条1項・4項により、過払金の請求対象になる消費者金融・クレジットカード会社の本社のある裁判所に提訴することが可能です。主な業者では以下のようになります。
| 業者 | 本社所在地 |
|---|---|
| アコム・プロミス・レイク・クレディセゾン・オリコ・ポケットカード・ニコス・イオンクレジット | 東京 |
| アイフル | 京都市 |
| セディナ | 名古屋市 |
| アプラス | 大阪市 |
| ライフカード | 横浜市 |
また、過払金は民法484条に基づき、請求する人の住所が義務履行地になり、民事訴訟法5条1号により請求する人の住所地に土地管轄が生じます。
したがって、過払金請求で裁判をする場合の裁判管轄に関する基本的な考え方は、業者の本社・請求する人の住所のいずれかで裁判をすることになります。しかし、過払金請求では、業者の本社・請求する人の住所地にある裁判所でなくても、裁判を起こせる場合があります。合意管轄・応訴管轄と言われるものです。
(4)合意管轄
裁判管轄について、民事訴訟法11条1項に「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる」と定められています。これは合意管轄と言われます。
消費者金融やクレジットカード会社は、全国展開している会社が多く、契約書上、営業所の所在地を管轄する裁判所について合意管轄が定められている場合があります。この規約があれば、多くの裁判所に管轄が認められます。例えば、業者の本社が東京、請求する人の住所が兵庫県でも、業者の営業所を合意管轄裁判所とする規約があり、業者の営業所が大阪市にあれば、依頼した弁護士事務所が大阪市の場合に、大阪の裁判所で裁判ができます。
(5)応訴管轄
裁判管轄について、民事訴訟法12条に「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。」と定められています。管轄違いの裁判所に提訴しても、業者が管轄違いの主張をしない場合は、その裁判所の管轄が認められるという規定です。
(4)の合意管轄の部分で記載した通り、消費者金融やクレジットカード会社は、全国展開している会社が多く、どの裁判所で手続きしても問題ないことが多いため、管轄違いの裁判所に提訴しても、管轄違いの主張をせず応訴してくることが多いと言えます。なお、請求する側は管轄違いと思っていても、業者側は合意管轄条項があるために管轄違いの主張をしていないというケースもあるかもしれません。
管轄違いの裁判所に提訴した場合、業者が管轄違いの抗弁を提出する場合以外に、裁判所が職権で管轄違いによる移送をする場合があります。このように応訴管轄は確実なものではありませんが、過払金訴訟では、応訴によって管轄が生じているケースがよくあ
弁護士によるまとめ
以上、過払金請求で訴訟をする場合の管轄について見てきました。過払金請求の場合、業者の本社・請求する人の住所以外でも、合意管轄・応訴管轄で多くの裁判所に管轄が生じるのが実態です。そのため、過払金請求では、裁判管轄の観点でどこの弁護士に依